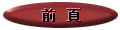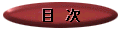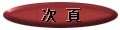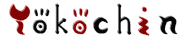


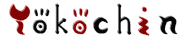

映画と傾向
映画は時代の傾向といったものを反映するのが普通である。以前、「ブックマーク」でご紹介した速水敏彦著「他人を見下す若者たち」の中で、筆者は1550年代中頃に邦画の内容が変化したという映画評論家、佐藤忠男の指摘へ触れていた。すなわち、それまでの邦画は泣く場面がきわめて多く、いささかセンチメンタルであったらしい。そして、
「太陽の季節」
「泣くことが善人のしるしであり、なぜ善人であるかといえば自分は被害者だからであるという、こうした意味で日本映画には泣くという芝居が文字通り濫用されていた」と述べている。感傷的であり、誠実であり、深刻であるということが、それまでの邦画ではもっとも正統的で価値のある作風だとされていた。当時の映画の鑑賞者は悲しみに堪え、まじめに努力する主人公と自分を重ね合わせていたものと推察できる。しかし、1950年代も後半へ差し掛かると主人公は急速に泣かなくなり、「エネルギー主義」が吹き荒れたそうだ。エネルギー主義とは、「太陽の季節(1956年)」や「嵐を呼ぶ男(1957年)」が代表する、禁欲的な道徳主義を蹴飛ばして欲望の解放をうたい、やりたいことをやるといった、人間のエネルギーを重視したものである。この変化へ反映されるとおり、その頃の時代は悲しみが減少傾向にあり、その傾向は現在ますます顕著だ。
いっぽう、それまでの泣きが主流の時代といえば、私の場合、黒澤明監督の「白痴(1951年)」や「生きる(1952年)」、あるいは溝口健二監督の「祇園囃子(1953年)」などを思い出す。黒澤が敬愛するドストエフスキーの名作を映画化した美しくも激しい愛憎劇「白痴」は、戦時中のショックで白痴になったと自ら語る純真無垢な青年、亀田欽司(森雅之)、彼は札幌へ帰る途中で無骨な男、赤間伝吉(三船敏郎)と知り合い、仲良くなる。その赤間は有力政治家の妾、那須妙子(原節子)に熱を上げていた。亀田も妙子の写真を一目見て心奪われる。また、そんな無邪気で美しい心を持つ亀田のことを親類の娘、大野綾子(久我美子)は誰よりも深く理解し、そして心惹かれていった。
「生きる」
「生きる」は、癌で余命幾ばくもないと知った初老の男性が、これまでの無意味な人生を悔い、最後に市民のための小公園を建設しようと奔走する姿を描いた黒澤監督によるヒューマンドラマの傑作である。市役所の市民課長、渡辺勘治(志村喬)は30年間無欠勤の真面目な男だった。ある日、彼は自分が胃癌であることを知る。命が残り少ないと悟ったとき、彼はこれまでの事なかれ主義的生き方へ疑問を抱く。そして、初めて真剣に申請書類へ目を通す。そこで彼の目に留まったのが市民から出されていた下水溜まりの埋め立てと小公園建設に関する陳情書なのだ。
「祇園囃子」は溝口が京都の花街、祇園を舞台に芸妓とそれを取り巻く人々の生態を細部まで徹底的に描き出した人間ドラマの傑作だ。祇園ではちょっと名の知れた芸妓、美代春(木暮実千代)のもとへ、母を亡くしたばかりの少女、栄子(若尾文子)が舞妓志願にやってきた。栄子の熱意に負けた美代春は、彼女を引き受けることになり、やがて1年間の舞妓修行を経て初めて店に出た栄子であった。ほどなく大会社の御曹司、楠田(河津清三郎)に見初められる。いっぽう、美代春も楠田の取引先である神崎(小柴幹治)から言い寄られるのだったが・・・・・・
「祇園囃子」
こうした泣きの映画は日本特有かといえば、そうでもない。時代の傾向が国によって違うのは当たり前だが、似通っている場合もある。たとえばチャーリー・チャップリンの名作「ライムライト(1953年)」は、チャップリンが演じるカルベロという一世を風靡しながら今は売れなくなった喜劇役者と、脚が動かなくなった原因をリュウマチのせいと思い込んで絶望し、ガス自殺を図るバレリーナ、テリー(クレア・ブルーム)の出会いで幕が開く。
自分の部屋でテリーを養生させるカルベロは「生きることに意味がない」と嘆く彼女へ、「人生は願望であり、意味ではない」と諭す。ところが彼自身、最近は仕事がなくなり、酒に溺れる毎日なのであった。役者も歳をとると人生を考え、深刻になるので客は遠ざかる・・・・・・と思うカルベロのもとへ久々に会社から電話が入り、1週間、ある劇場で出演してほしいと頼まれるのだ。しかし、そこの社長から最近は彼の名前を出しただけで劇場が出演を断ることも多く、自分の名前を出したくないなら違う名前で出演してくれていいと言われ、気まずい雰囲気が漂う。案の定、開演初日に彼の演技を見た観客がどんどん退場し、カルベロはたった1日で解雇される。
「ライムライト」
すっかり意気消沈して帰った彼を、今度はテリーのほうが励ます。励ましながら興奮して立ち上がった彼女は、自分が歩けるまでに回復していると初めて気づく。ここから励ます者と励まされる者との立場は逆転し、再びバレーの稽古を始めたテリーが練習の甲斐あって、その劇場のプリマドンナへと上りつめる。途中、かつて憧れた若い作曲家と出会い、愛を告白されるが、彼女は彼への気持ちを抑えてカルベロに結婚を申し込む。しかし、彼女の気持ちをじゅうぶん察するカルベロは、このまま同居していても彼女を悩ますだけだと悟り、独り家を出て・・・・・・
このような心が洗われるような映画は、最近あまり見かけない。「悲しみが多いほどやさしくなれる」というような悲しみは時代遅れなのであろうか? また、それらの映画から半世紀以上が過ぎた最近の傾向はどうであろうか? たとえば、今月の「お先に失礼!」でご紹介している「SUPER 8/スーパーエイト」や先月ご紹介した「マイティ・ソー」などのブロックバスター作がその性格上、時代の傾向をよく表わしていると思う。「スーパーエイト」などは心あたたまるものがありながら、「ライムライト」のような悲しみはない。まして「マイティ・ソー」の場合、いくら映画としての出来が良くても元はコミック・ヒーローだ。
「SUPER 8/
スーパーエイト」また、今月末(7月29日)の全米公開を控えた「トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン」など、試写会を見に行ってがっかりさせられた。シリーズ1作目「トランスフォーマー(2007年)」や2作目「トランスフォーマー/リベンジ(2009年)」と比べ、ほとんど内容がない上、美味しいシーンは予告編で紹介されていた以外、皆無なのである。アポロ11号が月へ着陸した時、無線の途切れた間に宇宙飛行士たちはトランスフォーマーを目撃していたという予告編が本編でどう膨らんでいるのか期待していたら、それは予告編だけのためのシーンであったという次第。そして、トランスフォーマーたちの間を縫って翼を着けた人間がフリーフォールをするシーンは、予告編の撮影風景のほうがむしろ興味を引かれた。
いっぽう、邦画でも最近ヒットした「さや侍」とか「アンダルシア 女神の報復」が時代の傾向を表わしているのだとすれば、これまた「白痴」や「生きる」のような泣きの世界ではない。邦画の場合、ヒットする映画の定番として劇場用、TV映画、大河ドラマ、その他を問わず必ず泣きのシーンがあるとはいえ、最近の映画と'50年代後半までのそれを比べると、ずいぶん質の違いがある。これは時代背景の違いであり、どちらがどうという問題ではない。
「トランスフォーマー/
ダークサイド・ムーン」ただ、今の時代のほうが生活は豊かになっている反面、心が寂しくなっていやしないだろうか? 日本はテロと無縁の平和な国という印象だったのが、「オウム真理教事件」あたりを境として大きな変化を遂げ、学校では「イジメ」や「不登校」が蔓延する。そういった最近の社会情勢は、主人公黒田康作(織田裕二)が「邦人テロ対策室」所属という先の「アンダルシア・・・」はもとより、やはり織田の主演シリーズで去年ヒットした「踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!(2010年)」で精神異常の犯罪者が登場するのを見てもわかるとおり、そのまま映画の中へ反映されているわけだ。
ちなみに、この「踊る大捜査線・・・」で定番「泣きのシーン」はといえば、係長まで昇進した主人公青島俊作が医者のミスでもう長くないと勘違いされ、同僚の恩田すみれ(深津絵里)から励まされる・・・・・・そう、やたら軽いのである。あるいは、「アンダルシア」で織田と共演する伊藤英明主演の「海猿シリーズ」も、毎回「泣きのシーン」でクライマックスを迎える典型だ。海上保安庁のエリートである潜水士の主人公仙崎大輔が、訓練中か救援活動中の事故で危うく死にかけたバディを助けたり、自ら死にかけた仙崎がバディから助けられ、彼の恋人で2作目からは妻となる伊沢環菜(加藤あい)は胸をなでおろす。その姿が観客の涙を誘う。
「踊る大捜査線
THE MOVIE 3
ヤツらを解放せよ!」
このように最近のヒット作を'50年代後半までの邦画と比べてみると、同じ泣きでも奥深さは天と地の開きがある。と同時、もう1つの大きな違いは宮崎アニメなども含めて今の邦画製作へ10社近くが係わっていると気づく。つまり、製作のゴーサインは10人近くかそれ以上のプロデューサーの合意が前提となり、当然ながら後世まで残るほどユニークな作風は期待できない。結果として「泣きのシーン」を含めて無難な線で決まる。それが'50年代後半までは東宝なら東宝、松竹なら松竹が自社で抱える監督へ製作を任せたため、彼らはサラリーマン監督であったにもかかわらず自分のスタイルを追求できた。いや、追求せざるを得なかった。
そういった中から生まれたのが黒澤であり、溝口であり、はたまた小津安二郎であり、山田洋次だったのは皮肉といえば皮肉だ。その後、彼らの個性豊かな作品が世界的に受け入れられるのと反して、最近日本でヒットした個性のない邦画は、ごく一部を除いてしょせん海外で評価されるとは思えない。かといって、スピルバーグがスポンサーとなった(言い換えれば製作総指揮の)「夢(1990年)」は今いちだったし、同じく「スーパーエイト」や「トランスフォーマー・シリーズ」でも、後者の3作目の出来がひどかったのは前述のとおりだ。物事すべて表があれば裏があるということだ!
横 井 康 和