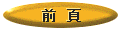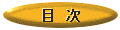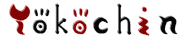


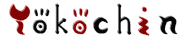

空中四万哩 (その6)
7月23日、一足早く東京へ着いた私は、さっそくキャピトル東急をチェックインし、まずはライブハウスのスタッフその他と電話連絡をとる。しかし、目指す相手が誰1人つかまらず、彼らのオフィスや自宅の留守電にメッセージを残した後は待つしかない。ジョージ・クリントン一行から何か知らせが入っていないか、やきもきしながら深夜も回り、連絡はないまま時間だけが過ぎてゆく。
私の仕事はクリントン他4名のビザを取り、残りのメンバー用のシナリオを書いた時点で完了した。だが、気持ちの上では全員が無事入国してコンサートを始めるまで終わったとはいえない。まんじりとしないまま夜が明け、カフェテリアへ降りていくと、昨夜、連絡を取れなかったスタッフがいる。これからクリントン一行を出迎えに成田へ向かうと言う。
ともあれ、ようやくわかったのは、私がヨーロッパを発つ前にホテルへ物を預け戻って来ることを伝えておいたため、ホテル側は同じ部屋を用意していた。それから、ライブハウス側で私の部屋を予約した時、別の部屋が押さえられた結果、私の身柄は2階へ、メッセージは9階へ送られたのである。いやはや、ドサクサの旅にはドサクサが付きまとうものだ。
スタッフが成田に出発した後、私はフロントで事情を説明し、9階へ引っ越す。ドアを開けるや電話のベルが鳴り、受話器を取る。4週間後に来日するギャップバンドのマネージャーだ。ここ何日かL・A(ロサンゼルス)の自宅へ電話を入れ続けていたらしい。事情を話し、打ち合わせのほうは1日余裕をもらう。せっかちな男である。
そうこうするうち、ステージ関係の書類を届けてくれたスタッフからクリントン一行が無事入国と聞いて胸を撫で下ろす。ホッとしたところで早めの昼食に決めた。食べながら、最初はピンと来なかった任務完了の充実感が、じわじわと心を包み込む。食べ終わってロビーに出たところへ、ちょうどクリントン一行の到着だ。
日本で彼らの顔を見た瞬間の感動たるや、何とも形容しがたい。16時間のバス・ツアー以来、彼らは私をすっかり仲間扱いするようになった。誰もがうんざりしているバス旅行を耐えた連帯感といおうか、彼らにとって、あれは一種の「イニシエーション(寮や特定のグループ等へ加わるための儀式)」なのである。それに私が合格したというわけだ。以来、「ユー・ガイズ(君たちは)・・・」と言えば、「ウィ(われわれ)」と訂正され、嬉しいような迷惑なような・・・・・・
と、ヨーロッパでは複雑な心境だったのが、こうして2日振りで見る彼らの人懐っこい笑顔は、ただただ再会を祝いたい気分にさせられる。初めて乗るライブハウスの送迎用バスで彼らと会場へ向かう途中、考えてみれば、日本に着いてまで彼らとバス・ツアーをやる自分が可笑しい。
会場でリハーサルも終わり、開演を待つ間、場内をブラついていると、アメリカ人組スタッフのフロアー・マネージャーから「ミッション・アコンプリッシュド(任務完了)、おめでとう!」と、声をかけられる。ラスベガスから来たドイツ系アメリカ人の彼女の本職はファッション・モデルだが、学生時代、国際ビジネスを専攻していたこともあって、アメリカ人組のまとめ役にスカウトされたのだ。
ジョージ・クリントン
の東京公演
彼女同様、他のアメリカ人組スタッフは暖かく迎えてくれる反面、どうも日本人組スタッフの表情が冥(くら)い。アメリカ人組は主にウェイトレスやウェイターで、音響や照明といった舞台関係の日本人組とは仕事内容が違う。それも1つの理由ではあるが、本質的な問題は意志の疎通にある。
彼らの職人気質(かたぎ)が、欧米のスタッフと舞台を作っていく上で、どうも裏目に出ているようだ。あるいは、まだオープンしたばかりで心の余裕がないだけかもしれない。そして、心の余裕といえば、自分自身は?
ただでさえドサクサの旅へ、1人の女性との別れと、もう1人の女性との出会いが重なった。じっくり考える余裕などないまま、その衝撃は潜在意識を満たしていたのがウィーン国立美術館で弾け、初めて自覚する。ただ、仕事の緊張感で頭の一線を保てたのは昼までの話、今や自慢じゃないが精神状態の不安定さなら誰にも負けやしない。
クリントン一行は無事入国し、間もなくショータイム、もはや(L・Aへの)帰国を余すのみだ。この際、徹底的に飲むと決めた私が楽屋へ行くと、バンドの連中は食事中である。食事を誘われて酒を誘い返す。なにしろアル中集団のようなバンドなので、出番前であろうが酒の影響は心配ない。また、少し煽れば、どんどん勢いづく。
食事中のビールから、食べ終わってワインの乾杯、そしてバーボンのストレートまでエスカレートし、「ジョージ・クリントン・アンド・ファンカデリック・オール・スターズ」のショーが始まる頃、私の血液中のアルコール濃度は間違いなく1.5前後だったと思う。VIP席に着き、スコッチ・ソーダをキメると、もはや「ファックド・アップ(酔っぱらい)」の域まで達した強み、心の赴くまま身体が浮いて気は沈む。
この時とばかりスタッフ連中へ説教を始めれば、いつしかグチに変わっているから最低だ。淋しさがこみ上げ、やりきれない気分で心の中身をぶちまけるうち、どういうわけかそこへ別れた女性と出会った女性まで登場し、2人を前に心はバラバラ、収集がつかない。そろそろ退け時と悟った私は、朦朧とする意識で会場を出る。人知れず消えるあたり、まだ救いがあったのに、キャピトル東急へ向かう途中は断片的な記憶しかない。これだけ酔うなんて、いったい何年振りだろう!
翌朝9時に目覚めると頭は空っぽだ。やたら心が軽い。昨夜の出来事を思い出そうとして、まず浮かぶのは、タクシーを降りる時、やたらチップをはずんだ記憶・・・・・・あれだけ酔って、なお経済概念に囚われているのだから情けない限りだ。ともあれ、この1ケ月の旅が何であったにせよ、昨夜エンディングは幕を下ろした。
新たな気分でカフェテリアへ降りるとファンカデリックのパーカッショニストがいる。昨夜、見過ごしたショーの後半はどうだったか聞けば、彼も途中で抜けて知らないと言う。さすがファンカデリックのメンバーだ。もっとも、マネージャーのミスで彼の楽器は揃っていなかった以上、文句のつけようがない。そのパーカッショニストの書いた曲をウォークマンで聴くうち、そろそろ出発の時間だ。続きはL・Aで聴かせてもらうと約束し、カフェテリアを出る。
ホテルのチェックアウトを終え、残る雑用を片づけるためライブハウスのオフィスへ向かう。数時間後、成田でJAL66便の通路側(アイル)シートに落ち着くと、改めて「旅の終わり」を実感する。それは「心の旅」でもあった。そして、終わりは始まりだ。人生の1里塚を1つ越したような感銘に耽りつつ、私を乗せたボーイング747機が最後の数千マイルへ向かって飛び立つ。
ポインセティア通りのわが家に戻り、数日間は非常事態へ備え、心の準備をしていたが、今度ばかりは劇的なニュースもなく平常の生活ペースに戻った。こうして、私の短くて長い空路4万マイルの旅が完結したのである。 (完)
横 井 康 和